『祝祭性と狂気 故郷なき郷愁のゆくえ』 渡辺哲夫
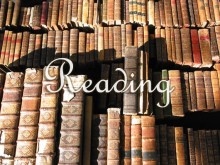
現代精神医学という封印を解く
本書については、ラース・フォン・トリアーの『アンチクライスト』のレビューのなかで、長めに紹介、引用しているので、そちらを先に読んでいただければと思う。
また取り上げるのは、『アンチクライスト』だけではなく、トルコのセミフ・カプランオール監督のユスフ三部作(『卵』、『ミルク』、『蜂蜜』)を観るうえでも、参考になるからだ。
ユスフ三部作では、ユスフという主人公の成長過程を追うのではなく、壮年期から青年期、幼少期へと遡っていく。そんな三部作の共通点として見逃せないのが、登場人物が発作を起こして倒れる場面が盛り込まれていることだ。それらは癲癇の発作のように見える。
●第一作『卵』
2:00を過ぎたあたりにその場面が出てくる。
●第三作『蜂蜜』
0:35あたりにその場面が出てくる。
『祝祭性と狂気』には、以下のような言葉が出てくる。
「たとえば現代精神医学も、その解くべき封印の一つではないだろうか。絶え難い苦痛、絶望などが症状であるならば、もちろん治療という形で病気を封印すべきと思うが、生命の輝きそのもののような狂気もあり、これは本来、悲惨不毛なだけの病気でないにもかかわらず、これをも精神科医療の名のもとに封印してしまうことが少なくない」
本書では、そんな立場に立って、狂気に陥った人間の深淵に<動物性>を見出し、<反・動物>と規定され歴史に取り込まれた人間が、<反・反・動物性>へと反転すること、言語的に媒介される前の透明な世界に肉薄すること、歴史の外部へと超出して<瞬間>を生きること、<動物性>へと帰郷することの可能性が掘り下げられていく。
ユスフ三部作もまた、発作という<狂気>を描くことで、歴史の外部へと踏み出し、生と死や夢と現実の境界を超える詩的なヴィジョンを獲得し、完結編である『蜂蜜』のラストで自然、あるいは<動物性>への帰郷を果たすように見える。
●amazon.co.jpへ