『哲学者とオオカミ――愛・死・幸福についてのレッスン』 マーク・ローランズ
- アク・ロウヒミエス, アピチャッポン・ウィーラセタクン, イエジー・スコリモフスキ, イギリス, セミフ・カプランオール, マーク・ローランズ, ラース・フォン・トリアー, 他者, 内田伸輝, 動物性, 想田和弘, 死, 渡辺哲夫
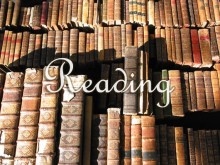
オオカミという他者を通して人間とは何なのかを考察する
想田和弘監督の『Peace ピース』(7月16日公開予定)の試写を観たときに最初に思い出したのがこの本のことだった。そこでぱらぱらと読み返してみた。
最初に読んだときも引き込まれたが、今では著者の言葉がもっと身近に感じられる。それは、『ブンミおじさんの森』、『アンチクライスト』、『四つのいのち』、『4月の涙』(野生のオオカミが出てくる場面がある)、『蜂蜜』、『エッセンシャル・キリング』といった作品を通して、人間と動物の関係に以前よりも鋭敏になっているからだろう。
マーク・ローランズはウェールズ生まれの哲学者で、本書では、ブレニンという名のオオカミと10年以上に渡っていっしょに暮らした経験を通して、ブレニンについて語るだけではなく、人間であることが何を意味するのかについても語っている。
↓ この人がローランズだが、いっしょにいるのはもちろんブレニンではない。ブレニンは、各地の大学で教えるローランズとともに合衆国、アイルランド、イングランド、フランスと渡り歩き、フランスで死んだ。ローランズはその後マイアミに移り、この映像はそこで撮影したものだ。
ローランズが本書で書いていることは、表現は違うが、渡辺哲夫の『祝祭性と狂気』のそれに通じるものがある。どちらも進化によって失われた“動物性”の意味を掘り下げ、それを呼び覚まそうとする。
『祝祭性と狂気』では、動物と人間が「瞬間」と「歴史」として対置される。動物は瞬間を生きる。進化した<反・動物>としての人間は、「生産労働の歴史」に取り込まれ、過去と未来に縛られ、憂愁、倦厭、嫉妬、苦痛に苛まれる。だからといって動物に戻ることは不可能だ。そこで、カンダーリという瞬間の狂気を糸口に、<反・反・動物性>という地平を切り拓き、動物性に帰郷にようとする。
ローランズは、サルを人間が持つ傾向のメタファーとして使う。サルは、幸福も愛も人生で一番大切なものも、コスト・利益分析の視点から見る。こうした定量化は時間に関わる。だから本書では、動物=オオカミと人間=サルが「瞬間」と「時間」として対置される。オオカミは瞬間を受け入れ、サルは瞬間をそのままではなく、前後の関係のなかでとらえる。
サルとはどういう動物か。「理由、証拠、正当化、権限。真に卑劣な動物だけが、これらの概念を必要とする。その動物が不愉快であればあるほど、そして悪意に満ち、仲直りの方法に無関心であればあるほど、正義感を火急に必要とするのだ。自然全体の中で、サルはまったく孤立している。サルだけが唯一、道徳的な動物となる必要があるほどに不愉快な動物だからだ。
わたしたちがもつ最高のものは、わたしたちがもつ最悪のものから生じた。これは必ずしも悪いことではないが、この点をわたしたちは肝に銘じなければならない」
そのことを忘れてしまうと、サル=人間は追いつめられる。いつかサル的なものから見離される。いや、すでに見離され、追いつめられていると考えるべきだろう。
「わたしたちの魂には、サルになるはるか以前、つまりこうした傾向がわたしたちを圧倒する前から存在していた部分もある。この部分は、わたしたちが自分自身について語る所説の中に隠されている。隠されているとはいえ、これを掘り起こすことはできる」
とここまで書いてきて、本書の内容が、想田監督の『Peace』のあとに観たもう1本の映画にも当てはまることに気づいた。それは内田伸輝監督の『ふゆの獣』。この本と絡めてレビューを書くことにする。
ちなみに想田監督の『Peace』については、「キネマ旬報」2011年7月下旬号(7月5日発売)に作品評を書いておりますので、ぜひお読みください。
●amazon.co.jpへ