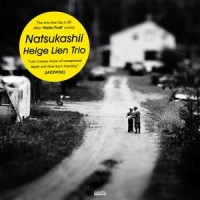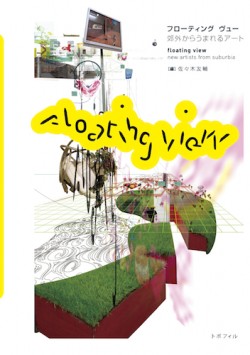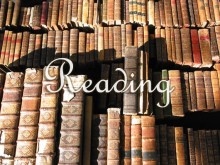Rudresh Mahanthappaが切り拓くハイブリッドな世界

文化的、伝統的、地理的な境界を揺さぶり、広がるネットワーク
読むのを楽しみにしていながらそのままになっていたall about jazz.comのルドレシュ・マハンサッパ(Rudresh Mahanthappa)のインタビューを原稿書きの合間にやっとチェック。このサイトのインタビューは基本的にボリュームがあるが、特にマハンサッパの場合は質問もたくさんあったはず。この数年、実に多様なコラボレーションを繰り広げているからだ。
それは彼がインド系であることと無関係ではない。マイナーなレーベルからアルバム・デビューした頃には、インドというレッテルを貼られ、ラヴィ・シャンカールをゲストに…みたいなアドバイスをされることもあったらしい。もちろん、彼が求めていたのはそんな音楽ではなかった。
39歳のマハンサッパと75歳のバンキー・グリーンというまったく世代の異なるアルトサックス奏者がコラボレーションを繰り広げる『Apex』(2010)は、その当時、彼がどんな音楽を求めていたのかを示唆する。
バンキー・グリーンのことは、ノース・テキサスからバークリーに出てきて音楽を学んでいるときに、サックスの講師ジョー・ヴィオラから教えられた。グリーンのアルバム『Places We’ve Never Been』を聴いてぶっ飛んだ彼は、デモテープを送り、助言を求めた。それが関係の始まりだ。